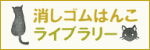Atelier POCO A POCO
イレイサースタンプ&シャインカービング
アトリエ POCO A POCO うえむらゆみこ
JR安城駅より徒歩7分、愛知県安城市にある小さなアトリエです。 Tweet
エッセイ
エッセイ『消しゴムはんこに出会えて』
平成二十三年四月。
桜の花びらが舞い、新しい季節を迎え待ちに待った小学一年生の入学式。
新一年生のいる家族は期待に胸を膨らませワクワクと新品のランドセルを準備して我が子が腕をとおす日を心待ちに入学式を迎えるのだろう。
長女の体調が悪化していったのは小学校の入学を控えた幼稚園の年長の頃だった。
長女が普通じゃないと気付いたのは下の子が生まれてからだ。
長女はすぐに風邪をひき、熱を出し、冬の間は冬と言っても秋ごろから春ごろまで一年の半分はずっと風邪をひいていた。
今思えば風邪ではなかったのかもしれない。
次女は風邪をひいても一週間もすればけろっと治ってしまうことに驚いた。
長女は冬の間ずっと体調が悪く布団から起き上がれない。
病院に行くと「風邪」だと診断され風邪薬を処方された。
その症状に加えて暑くなると身体中に何十個もの水ぶくれができ化膿した。毎日が必死だった。
複数の病院を受診した。それでも原因はわからず「風邪」や「水いぼ」だと言われた。
そんな状況の中、長女は小学一年生になった。
入学式に出席できるかどうか不安だったが何とか出席した。
水ぶくれで身体中が痛みランドセルを背負うどころか歩くのもやっとの状態。
一学期が始まったが想像していたピカピカの一年生とはほど遠く長女はみるみると衰弱していくのが見てわかった。
まず朝起き上がることができない。
休みがちだったが、調子の良い日には一緒に付き添って登校した。
勉強どころではない。
宿題どころではなかった。
だんだんと歩けなくなってきた。
六歳の身体は抱っこやおんぶをするには重すぎて本来なら三女が使うべきベビーカーに乗せて登校した。
当時も内科や皮膚科などの病院を探しては受診することを繰り返していたが原因はわからず。
その当時、三歳の次女と生後半年の三女を抱え病院に行くことだって精一杯だった。
そして、ついに長女は動けなくなってしまった。
正直、このまま死んでしまうのであろうと思うような状態だった。
顔色は悪く食欲はなく歩くこともできず…ただ水ぶくれ以外には見た目にはどこが悪いのかわからない。
インターネットで調べては有名な先生がいると知ればたとえ遠方の病院でも必死で連れていったが原因はわからず。
そしてついには血便が出て紫色の斑点が全身にたくさんできた。
顔から足先まで紫色の無数の斑点ができて人相は変わってしまった。
そのあまりにもかわいそうな姿に私はこう思った。
いくつもの病院にかかったけどさすがにこの姿を見たら入院させてもらえないだろうか。治療してもらえないだろうか。
すぐに近所のかかりつけの内科へ行き安城市で一番大きな総合病院へと紹介状を書いてもらい受診した。
そして私の予想通りついに入院になった。入院さえすれば何とかなるのではないか、詳しく検査をしてもらえるのではないか、助かるに違いないと、原因がわかるはずだと、そう確信した。
そして…大きな総合病院でたくさんの検査をした。
それなのに、やっぱり原因は不明だった。
その時、主治医ではなかったのだが若い先生が話を聞いてくれた。
今までのこと、七つも病院にかかったこと、長女だけ生まれた時から何かおかしいこと。その若い先生はたくさんの文献や症例を調べてくれて、その一生懸命さは私に負けないくらいだった。
そして…ついに。
十万人に四人しかかからないという腎臓の病気かもしれないということを突き止めてくれたのだ。
しかし…。私たちが住んでいる安城市内に小児腎臓の専門の医師は一人もいなかった。
名古屋にある小児腎臓科に紹介状を書いてくれてすぐに転院手続きをした。
私は長女の入院に付き添い主人が会社を休んで病院の送迎や下の子どもたちの面倒をみていた。
当時、尿検査も何度もしていたのに蛋白が出ていなかった。
蛋白が出ていたらすぐに腎臓病を疑うのだが検査はことごとく正常だったのだからしょうがない。
転院して詳しい検査をした。
そしてあの先生の予想通り腎臓の病気「急速進行性糸球体腎炎」だと病名を告げられた。
その病気は名の通り腎臓の糸球体が急速に損傷していき、十ヶ月以内には腎不全に陥るという何とも残酷な病名を告げられた。
やっと原因がわかった喜びよりもあまりにも残酷なその病名に言葉を失った。
まだ六才。
ピカピカの小学一年生。
七才には腎不全になる。
腎不全になっても透析すれば生きていける。
ただ…小児の透析は大人と違って毎日十時間が必要だった。
なんで…若すぎる。
七才から毎日十時間の透析だなんて。
腎炎は簡単に言うと栄養分を尿と一緒に排出してしまう。
正常なら腎臓でろ過をされて栄養分は体内に不要なものだけが尿として排出される。
それが栄養分まで排出されてしまうのだ。
だから身体はだるく調子が悪い。
生まれてからのこれまでのことがいろいろとつじつまがあった。
私は自分を責めるばかりだった。
健康に産んであげられなかった私に責任があるのではないか。
そんなことで散々自分を責めた上に心ない言葉を浴びせられることもあった。
「妊娠中に無茶をしたのではないか」
「悪いものでも食べたのでは?」
「なんで腎臓病なんかになってしまったのだ?原因は?」
立ち直れないほどに傷付き自分を余計に責めて苦しんだ。
急速進行性糸球体腎炎に陥る原因は解明されていない。
絶望しかなかった。
そして長い入院生活が始まり、自力で歩けない長女は六才なのにオムツを履いて移動は車イス。
体調の悪い日も多く泣いてばかりで介助が必要だったため、私も二十四時間付き添うしかなかった。
次女と三女を保育園に入れて主人が一人で家事育児をすることを一番に考えたが、当時の主人の仕事は早いときは朝六時には出発し帰りは遅いと午後九時を過ぎた。
それほど長時間預けられる保育園は無認可を含め見つけることができなかった。
日曜出勤もあるのだが大抵の保育園は日曜休みだ。
これ以上会社を休めない。
いろいろな方法を考えた。
ベビーシッターはこれから長期に渡る入院生活を考えると費用がかかりすぎる。
シッター代は丸一日みてもらうと二人分で二万円を超えた。
次女と三女を祖父母にあたる私の両親にみてほしいところだったが私の母は乳がんになり当時闘病中であった。
父は母の入院先に通っていてとても孫を預けられる状態ではなかった。
そこで主人の実家がある熊本の義両親のところに二人を預けることになった。
三女はハイハイができるようになり可愛い盛りだったが、それまで完全母乳で育てていたのに突然授乳をやめて粉ミルクで飲めるよう哺乳瓶の練習をした。
なかなかうまく哺乳瓶で飲むことはできず、私は突然の断乳により乳腺炎になり心も身体も本当に辛かった。
次女はやっと慣れてきた幼稚園に休園届けを出した。
あの頃のことを思い出すだけで胸が張り裂けそうになる。
そして私と長女の長い二人きりの入院生活が続いていった。
もう絶望しかなかった。
数ヶ月後には腎不全になる。
病室では熟睡することができず悪いことばかり考えた。
長女が不安がるため狭いベッドに一緒に添い寝した。
この入院は病気の完治のためではなく腎不全になるのを待つという地獄のような入院生活だった。
治療が始まったが副作用の強いステロイドを投与する治療だった。
最初は内服だったのだがパルス療法といって直接点滴で身体の中にステロイドを入れるという大変副作用の強い治療も行った。
そのせいで顔はパンパンに腫れて血圧は上がりそれを下げるためにさらに血圧の薬も服用した。
見た目にも本当に過酷な状況だった。
病院で生活していると日用品や私の食料など買い出しに行かなければならない。
病院から外へ出るとそこには普通の日常があった。
ちょうど三時頃になると小学生たちの帰宅時間に重なり楽しそうな笑い声が町中に響いていた。
スーパーに行くとたくさんのママたちが買い物をしている。
私はその光景がとてつもなくうらやましく心に突き刺さった。
あの小学生たちは毎日ランドセルを背負って学校に行く。
本当なら私の娘もピカピカの一年生になるはずだった。
自宅のリビングに起きっぱなしの腕をとおすことのない新品のままのランドセルを想像する。
あの買い物をしているママはこれから自宅に帰り家族のために夕飯を作るのだろう。
ハンバーグだろうか…そういえば次女もハンバーグが好きだった。
その夕食を囲む家族の団らんがとてつもなくうらやましく思えた。
私の夕食は…今日もカップラーメンだ。
病院の給湯室でお湯を入れて割り箸で食べるカップラーメン。
そんな病院の外でふいに出くわす幸せそうな日常に気が狂いそうだった。
入院していたのは小児専門の病棟だった。
非常に悲しい出来事だが病院で亡くなる子どももいた。
ご両親の気持ちを想像するとおかしくなりそうで必死に想像しないようにした。
長女は幸い命にかかわる病気ではない。
亡くなったお友達のことは長女に遠くの病院へ転院したと嘘をついた。
お母様がそうしてくれと言ったからだ。
私は人生で一番悲しい、辛くて悲しい嘘をついた。
熊本にいる次女と三女は元気だろうか。
面倒をみてもらっている義実家の家族は突然二人の幼い子を預かることになりどれほど大変だろうか。
パルス療法の甲斐もあって長女は少しずつ元気になっていった。
車イスなしで、自力で歩けるほどに回復した。
だけど完治することはない。
いつかは腎不全になるのだ。
それでも斑点が消えて浮腫が取れて元の顔に戻り元気になっていく姿がとても嬉しかった。いったいいつまで入院するのだろう…。
三ヶ月や四ヶ月で退院できるとは到底思えない。
向かいのベッドの腎炎の女の子はすでに一年以上ここに入院していると言っていた。
次女と三女を熊本に預けっぱなしという訳にもいかない。
三女の予防接種の案内だってたまっていく一方だった。
(結局熊本の義母が安城の保健所に電話で掛け合ってくれて熊本で予防接種は受けられることになった)
当時の問題や不安は山積みだった。
あげたらきりがない。
絶望と自分を責めるばかりの不安だらけの毎日。
そんなとき…。体調は悪いはずなのにいつも長女は明るかった。
ばかなことばっかり言って笑わせてくれる明るい長女を見て。
私も何かしなくては、とふいに思った。
何でもいい、何でもいいから病室でできることをやろう。
そして…病室の狭いスペースでできること。
そうだ。消しゴムはんこを彫ろう。
幸いなことに病院のすぐ近くにある百円ショップで消しゴムはんこの材料を簡単にしかも安価に入手することができた。
私は消しゴムはんこを少しだけ彫ったことがあった。
子どもたちの写真を飾る時に消しゴムはんこを捺して作品を作ったことがあった。
独学だったけど何となくやり方がわかったので道具や材料に迷うことはなかった。
病室で最初に彫ったのは長女の似顔絵はんこだった。
似顔絵を描き消しゴムに写してデザインカッターで彫った。
長女はとても喜んでくれた。
いろんな色のインクで一緒にペタペタと捺して楽しんでいると…。
隣のベッドの男の子が「ぼくもほしい」と言ってくれた。
私は嬉しくて車のお名前はんこを彫ってプレゼントをした。
そこから隣の病室へ、そのまた隣の病室へと広がり、小児腎臓病棟のみんな、はたまた隣の病棟である小児心臓科の子どもたちのはんこを彫った。
はんこは彫るだけでなく捺す楽しみがあった。
食事に付いてくる牛乳パックやプリンの入れ物に紙を貼ってはんこを捺したりみんなでメッセージカードを作ったりした。
病院には行事がたくさんあった。
七夕、ハロウィン、クリスマス、ひな祭り…。
病院で誕生日を迎える子どもはたくさんいた。
誕生日会でプレゼントするバースデーカードもたくさんはんこで作った。
病棟内でスタンプラリーをしたり、時には消しゴムはんこを捺して仕上げるワークショップの真似事をするようになった。
私は子どもたちが喜んでくれるのが嬉しくて毎日夢中ではんこを彫った。
ある時、一週間の検査入院にきた、あやちゃんという女の子のママが私の消しゴムはんこを見てこう言った。
「そんなに上手なら資格でも取ったらいいのに」
私は驚いた。
消しゴムはんこに資格があるのを知らなかった。
そして、あやちゃんママからイベントに出展しているという話を聞いた。
そしてさらに驚いた。
彫ったはんこを買ってくれる人がいるという。
いま思えば、あやちゃんママは消しゴムはんこ作家さんだったと思う。
たった一週間だったけど消しゴムはんこの世界を私にたくさん教えてくれた。
連絡先も何も聞いていない。
私の名前も告げていない。
病院では自分の名前なんか呼ばれることはなく、あやちゃんママと、このちゃんママだったのだ。
名古屋に住んでいるあやちゃんという当時二歳の女の子のママ。
手掛かりはそれだけだけど、もう一度会うことができるのなら…。
会いたい。
会ってお礼を言いたい。
そして私も消しゴムはんこ作家になったことを伝えたい。
たとえ今私の作家名をあやちゃんママが知っていたとしても、入院中はノーメイクにパジャマのような格好だったからきっと気付いていないだろう。
あやちゃんママはまだ作家を続けているのだろうか。
私は消しゴムはんこの資格を通信講座で取ることにした。
時間はたっぷりあった。
充分すぎるほどに時間はあった。
目標ができたことでさらに消しゴムはんこにのめり込んだ。
はんこの持つ力はすごい。
はんこには不思議な力があった。
ただ消しゴムを彫るだけではない。
噂を聞いて知らない人が他の病棟からわざわざ私を尋ねてくることがあった。
「うちの子どもにも消しゴムはんこを彫ってほしい」とか「噂の消しゴムはんこを見せてほしい」とか「彫り方を教えてほしい」とか。
みんな材料費を払うと言ってくれたが百円のハガキサイズの消しゴムを十二等分に切って三センチ角の消しゴムを使っていたので材料費は一個九円ほどだった。
消しゴムはんこはお金のかからない趣味だ。
入院当初は長女と看護師さん以外しゃべらない生活だったのにたくさんの人と交流するようになった。
私と長女は病室から出てデイルームで一日を過ごすことが多くなり生活にはりがでた。
消しゴムはんこのおかげで病棟という小さな閉塞的な世界の中で交流が生まれた。
同じ腎臓病の子供を持つママたちとは心より本音で話せることができた。
この悩み、辛さをわかってくれる数少ない理解者だった。
入院中に一緒だったママたちとは今も交流が続いている。
夜寝るときにだんだんと病気のことは考えなくなった。
明日はどんなはんこを彫ろう。
うさぎさんのデザインの図案にはリボンをつけようか。
不思議なもので消しゴムはんこのことを考えているとよく眠れるようになった。
それまでの入院生活とは一変したのだ。
長女の体調が少しずつよくなり病院内にある「院内学校」に通うことになった。
小児の専門病院だったので長期入院の子が多く院内学校に通っている小中学生は十人もいた。
そこには小さいけれど立派な日常と生活があった。
そしてびっくりしたのは院内学校もちゃんとしたひとつの「学校」であった。
地元の安城市の小学校から「転校」しなければいけないのだ。
私は久しぶりに安城に帰り小学校へ転校の手続きに行った。
自宅にも寄ったのだがガラーンと静まり返ったリビングに新品のまま置いてあるランドセルに涙がにじみ長居はしなかった。
何よりも親しくなった同じ病室のママに長女のことを頼んできたので現在の我が家である病院に一刻も早く戻らなければいけない。
すぐに小学校へと向かった。
数日しか通っていない小学校だから正直思い入れはない。
児童たちの明るい声に複雑な気持ちはあったが無事に転校手続きをした。
これで、食べてもいない給食費が引き落とされることはないし、旗当番が回ってくることもない。
(入院中でも当番日には朝電車で急いで一旦帰って旗当番をしてまた病院に戻っていた)
転校の手続きに行った時、担任の先生からクラスの何人かを連れてお見舞いに行きたいと言われたが申し訳ないが丁重にお断りをした。
数日しか通っていない小学校にお友だちはいなかったし、一年生のうちに地元の小学校に戻れるとは到底思えなかった。
クラスのみんなからお手紙をいただいたのだが、そこにはそろって平仮名だけのかわいい文字で「はやくげんきになってね」「いっしょにがっこうであそぼうね」と書かれてあったが申し訳ないけど、元気になることはない、走り回って遊ぶことはできない、治ることはないと思ってしまった。
わざわざ名古屋の病院にお見舞いに来てくれると言ったが病棟は無菌室があり子どもの訪問は禁止されていた。
そんなことをいろいろ説明するのが面倒でもう転校するのだし急いで病院に戻らないといけないし「名古屋まで遠いのでせっかくですがお見舞いはお気持ちだけで…」と丁重にお断りをした。
うまく言えないが転校できて少しスッキリした。
長女は平日の十時~三時に院内学校に通うことになった。
お昼に一旦戻って病棟で食事をとるのだが(一人一人の病状によりメニューが違うので)長女が学校に行っている午前と午後に私は自由な時間ができた。
それで気付いたのだが長女が産まれてから「自由な時間」は初めてだった。
いつも看病で必死だったし、たとえ主人がみてくれている間も気がかりはあって集中できなかった。
院内学校に行っている間は安心して自由になれるという意味で何年かぶりの自分の時間だった。
私はその時間をすべて消しゴムはんこに費やした。
みるみると上達していくのがわかる。
楽しい。
消しゴムはんこがすべてだった。
長女は院内学校に通うようになって以前に増して明るくなり楽しそうだった。
院内学校の担任の先生は小学一年生の幼い娘に予想外の教育をしてくれた。
先生が教えてくれたのは「勉強」ではなく「勉強のやり方」だったのだ。
持病があると毎日継続的に勉強をするのは難しい。
入院中、検査の数値が悪い時や体調が悪化している時には院内学校には通えず病室で過ごす。
だから先生は持病のある子こそ誰かに勉強を教えてもらうのではなく体調の良い時に自分で勉強を進めるという術を伝授してくれた。
教科書さえあれば学校に通えなくても先生に教えてもらえなくても勉強なんてどこでもできる、そう言っていた。
だから長女は院内学校の先生に教えてもらうのではなく、体調の良い時に病室でどんどん教科書を進めていった。
院内学校に行ける日は理解していない部分を重点的にマンツーマンで教えてくれた。
もちろん体調が悪いときにはまったく勉強なんてできない日が数日間続く。
それでも自分のペースで学習を進めることができた。
あの時の院内学校の先生は長女の今後の生き方を左右する重要なことを教えてくれた。
その後季節が移り変わり。
入院した時は初夏だったのだが、病院でお正月を過ごすことになった。お正月は一時的に外泊する患者さんばかりだったがちょうど体調が悪くて外泊許可が下りなかった。小児病棟のお友だちはみんな外泊許可が下りた。
病院全体を見てもわざわざお正月に手術をする人なんてほとんどおらず、外来もお休みで院内は見違えるほどとても静かだった。
大晦日の日、長女が眠った後、私は携帯のワンセグで紅白を見て除夜の鐘を聞いた。毎年お正月になるとあの夜を思い出す。
病院で過ごしたせつない年越し。
何とも淋しいお正月だったが、元旦からやっぱり私ははんこを彫った。
そして季節は春になり、体調の変わらないままこれ以上病院で治療できることはないと、通院治療に切り替えることになり、退院することになった。
七ヶ月間の入院生活。本当に長かった。
退院したところですぐに地元の小学校に通える訳ではなかったがそれでも退院は嬉しかった。
平成二十四年四月。
自宅に戻ってきて私が下の子をみることができるようになり、主人がすぐに次女と三女を熊本に迎えに行った。
長女は自宅療養になり週に一度名古屋の病院まで通院する生活になった。
次女は幼稚園の年中組になり休園していた園に再入園することになった。
三女は離れたときにハイハイをしていたのだが再会した時には一才半になり走ってきたのには大変驚いた。七ヶ月間会いに行けるわけでもなく、三女には七ヶ月ぶりに会ったのだ。
私は三女のつかまり立ちも歩き始めも見ていない。
熊本から写真を送ってもらってはいたが、ハイハイから急に走り出した三女を見て、赤ちゃんから急に子どもになった三女を見て戸惑うばかりだった。
上の二人を子育てしていたから大丈夫だとなぜか自信があったのだが、ことごとく三女の扱いには苦戦した。
まず第一に、私のことを(たぶん)覚えていなかった。
抱っこしようとしても泣きじゃくるばかりでずっと一緒だった次女の後ばかりを追っていた。
離れたときはまだ離乳食も始まっていなかったからどんな食べものが好きなのか、そんなことさえわからなかった。
次女が幼稚園に行っている間、私は三女の扱いに本当に苦労した。
いくら産んだのが自分だとしても育てていないというのはこういうことなのかと思い知らされた。
きっと私のことを母親だと認識していない。
三女との生活に戸惑いながら、長女の世話もしつつ、新しい生活をしていくしかなかった。
必死だった。
長女の通学許可が出たのは初夏だった。
最初は小学校にいる時間は一時間、慣れてきたら午前中、という感じで少しずつ通学する練習をしていった。
腎炎は風邪をひくと重症化して治りが遅く蛋白が出てしまう。
蛋白の量が多くなると再入院になる。
ぜったいに風邪をひかないよう主治医から言われ一年中マスクをした。
また疲れると蛋白の量が多くなってしまうので走るのも運動も禁止だった。
それに加えて水ぶくれは「異汗性湿疹」というもう一つの病気が原因だとわかり、夏場は汗をかいてはいけない、冬場は風邪をひいてはいけないという、子どものいる家庭にとって無理難題な制限があった。
運動会は本部のテントの下に一人席を作ってもらい、決して汗をかかないよう保冷剤やウチワを使って暑さをしのぎながらも参加した。
長縄跳び大会は縄を回す役にしてもらい手に豆ができるほど回す練習をして楽しそうに参加した。
それと共にそろそろ腎不全になる日がやってくるのだろうかという不安がいつも頭の中にあった。
一日一日をこなしていくのがやっとでその頃は消しゴムはんこをお休みしていた。
平成二十五年四月。
長女は小学三年生になった。
ステロイドの副作用で低身長だ。
低身長以外の見た目は普通なのだが様々な制限があり腎臓病を理解してもらうのは難しかった。
体調の良い日と悪い日の差が激しく学校を休んだり早退する日も多かった。「このかちゃんは休んでばかり」「ずる休み」よくそう言われていた。
それで長女と二人で考えて「このかの取り扱い説明書」というものを作ってクラスのみんなに配布してもらった。
【このかの取り扱い説明書】
私は腎臓病です。見た目には病気だとわかりません。
腎臓病は人にはうつりません。
からだがだるくてお休みをすることが多いです。
私の腎臓が動かなくなったら毎日透析(とうせき)をします。
透析がうまくいかなかったら腎臓は二つあるのでお母さんから一つの腎臓をもらいます。そうすれば生きていけます。
…というように子どもにもわかるように長女のイラスト付きで腎臓病を説明して配布してもらった。
それを読んでくれたクラスのみんなや同じ通学団のみんなには病気を理解してもらうことができた。
それから毎年クラス替えのたびに「このかの取り扱い説明書」を配るようになった。
この頃から考え方が変わってきて、もう病気を治すことはできないと悲観するのをやめよう。
うまく病気と付き合っていこう。
長女にとっては一生腎臓病だ。
死ぬまで上手に腎臓病と付き合っていこう。
そう考えるようになった。
ただ気がかりだったのは…。
透析が始まってしまったら旅行に行けなくなってしまう。
私は旅行が大好きで今のうちに連れて行ってあげたいと思いきって家族五人でプーケットに行った。
主治医にも相談して許可をもらい服用している薬の英文の文章を作り(機内持ち込みする際に必要)準備は万端にした。
幸い旅行中は長女の体調はよく人生最後になるかもしれない海外旅行を思いきり楽しんだ。
そして次女と三女も少しずつ成長した。
三女との間に失われていた信頼関係も時間と共に取り戻すことができるようになった。
三女が「ママ」と呼んでくれた時には、それはそれは嬉しかった。
そして三女が二歳になり余裕がでてきたので私は消しゴムはんこを再開した。
入院中に磨いた腕は少しも劣ってはいなかった。
育児の合間にはんこを彫る。
それはこの上ない私の楽しみであった。
私は彫ったはんこをブログに載せるようになった。
そして…信じられないことがこれから次々に起こるのだ。
なぜだか意味不明だが消しゴムはんこのブログランキングの順位がみるみる上昇していったのだ。
愛知県の安城市というのどかな田舎町に住む専業主婦が書いている趣味のブログが。
消しゴムはんこはまったくの独学だった。
そんな素人がガラケーで書いているブログのアクセス数は日増しに増えていく。
インターネットは本当にすごい、そう思った。
そしてブログランキング上昇と共に信じられない話がたくさん舞い込んできた。
雑誌での紹介、テレビ出演、インタビューの掲載、トークショーや講演会。
アトリエ(自宅の六畳の狭い洋間)に取材にきてくれたり、ラジオで長女の話をしたこともある。
講師やイベントの依頼も次々にたくさん舞い込んだ。
すべての依頼はブログのメールフォームに届いた。
そして信じられないような多忙な日々を送ることになるのだが、毎日が本当に楽しかった。
楽しくて仕方がなかった。
消しゴムはんこも育児も家事も家族で過ごせる普通の生活も。
すべてが楽しかった。
私が消しゴムはんこを彫っていると、はんこを捺していると、みんなは笑顔になった。
娘たちも私自身も笑顔に溢れていた。
平成二十九年四月
月日は流れ、長女は中学一年生になった。相変わらず低身長なので子どものようなあどけない中一だった。
そんな長女が運動部に入りたいと突然言い出した。
小学生の間、運動は禁止されていた。
なぜ運動部なのか理解できなかったがどうしても卓球部に入りたいという意思は固かった。主治医と相談して無理をしないことを条件に卓球部に入る許可が下りた。
そして私は長女にこう告げた。
「卓球部に入るのなら誰よりも努力をしろ。人より疲れてしまうのなら体力が持たないなら人の半分の練習で成果を出せる効率の良い練習方法を探しだせ。体力のなさはテクニックで、頭脳で勝負しろ。運動部に入るのなら目標はオリンピックだ。その覚悟がないのならやめた方がいい」
私は病気をハンデにしてほしくなかった。
運動部の大変さをなめてもらっちゃ困る。
やるからには何かを得てほしかった。
そして、中二の夏。安城市の卓球大会で、個人戦ベスト十六位という成績を残した。信じられなかった。
私が望んでいた以上の成果をだした。
ただ…誰よりも努力をしていたのは知っていた。
世界卓球の動画を毎日見て研究していたし、リビングでは常にラケットを持っていていつも素振りをしていた。
小学生の頃、院内学校の先生が勉強のやり方を教えてくれた。
そのおかげで小学生の間のテストはほとんどが満点だった。
学校に通えない日が多かったけどそれでもテストは満点だった。
努力をしていれば報われるということを長女はいつも教えてくれた。
私の消しゴムはんこの方は、講師業、イベント出展、連載などの執筆、などなどで多忙なスケジュールだった。
しかし、フリーの作家なので長女の体調に合わせてお休みを取ることができる。
作品製作や執筆などは自宅アトリエで行うので早退する時などはすぐに迎えに行くことができた。
長女の通院や入院だってスケジュールに組み込むことが容易にできた。
外に働きに出るのは無理だったから私と家族にとっては消しゴムはんこ作家という職業はとても合っていたのだ。
平成三十一年四月。
長女は中学三年生になった。
いよいよ受験生だ。
低身長に悩んでいたのに薬の服用をやめてしばらくすると身長が一気に十センチ以上も伸びた。今は中三女子の平均的な身長にまで追い付いたのだ。
先日の卓球大会では個人戦で安城市三位という、信じられないような快挙を成し遂げた。
オリンピックではないけれど銅メダルじゃないか。
私にとっては紛れもない銅メダルだ。
そして今長女は生徒会に立候補すると隣で選挙のポスターを描いている。
私と同じで絵を描くのが大好きだ。
やるからには当選してほしい。
長女はいつも楽しそうだ。
何よりそれが嬉しいことだ。
相変わらず腎臓病の方は通院で治療している。
あの時…。
六歳の時に十ヶ月以内に腎不全になると告げられたのに信じられないがまだ自分の腎臓を使っている。
それどころか卓球部のキャプテンをしているくらい元気だ。
急速進行性糸球体腎炎。
十万人に四人がかかる病気。
症例数が少ない分、きっと望みはたくさんある。
長女は腎不全にはならないかもしれない。このまま一生過ごせるかもしれない。
いやきっとこのまま腎不全にならないだろうとさえ思う。
蛋白は出ているけれど卓球ができるほど元気だ。
毎日学校にだって通っている。
うまく病気と付き合っている。
それに…もし今、腎不全になったとしても。
身体が大きくなった。
六歳の時とは違う。
毎日十時間の透析はもう必要ない。
もう大人の身体だから週に四日の透析で大丈夫だ。たった週に四日だ。
それで生きていける。異汗性湿疹だって水ぶくれは自分で対処ができるようになった。
薬を塗るのか水ぶくれをつぶした方がいいのか自分で判断をして処置をできる。
昔のようにかきむしって化膿することはない。
八年前、長女が腎臓病だと診断された頃。
いずれこんな生活ができるなんて夢にも思わなかった。
あの時は絶望しかなかった。
私は一生長女の面倒をみていくものだと思っていた。
こんな生活ができるなんて想像さえできなかった。
私は何度も消しゴムはんこに救われてきた。
あの時、はんこを彫っていなかったらどん底のままだったかもしれない。
希望を見出だせなかったかもしれない。
何よりも消しゴムはんこのある生活のおかげで明るく前向きに過ごせるようになった。
今もそう。
消しゴムはんこはたくさんの奇跡とたくさんの希望を与えてくれた。
きっと何か不思議な力を持っている。
絶望と悔しさの連続だった毎日を希望のある未来へと導いてくれた。
消しゴムはんこにできることは、星の数ほどたくさんある。
消しゴムはんこに出会えてよかった。
本当によかった。
そして、私はこれからも消しゴムはんこの楽しさを、その可能性を、世界中の人たちに伝えていきたい。
消しゴムはんこで新しい道を切り開いていきたい。
辛さや悲しみを抱えている人たちを消しゴムはんこで笑顔にしたい。
そして、子どもたちが、世界中のみんなが消しゴムはんこで幸せになれますように。笑顔の絶えない毎日を送れますように。
そう願いながら…。これからもはんこを彫り続ける。
そして、今日も消しゴムはんこを彫ろう。
消しゴムはんこ作家 うえむらゆみこ